お金を貯めるにはお金の管理をするための知識が必要です。
そのためには簿記を学ぶことが近道

簿記3級は勉強すれば誰でも取得できる公的資格です
一生お金に困らない知識を、
資格という体系的に勉強できる仕組みを利用して身につけましょう。
サラリーマンが本業の合間に、
無料で1発合格したノウハウを、
これから勉強する方や
確実に地道に合格したい方に向けて、
全て惜しみなくお伝えします。
使用した教材
ふくしままさゆきさんのYouTube
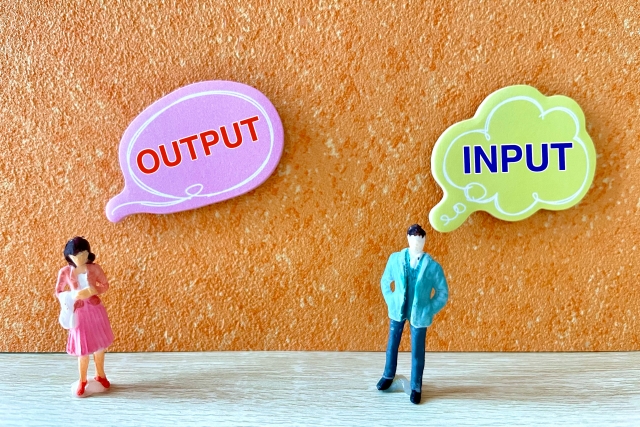
基本はふくしままさゆきさんのYouTubeで説明している通りに進めます。
ふくしままさゆきさんは、「簿記系YouTuber」として知られる日本のユーチューバー。
合格者続出の大好評講義、国内No. 1の解説量、簿記3級の講義はすべて無料、「アウトプットしまくってパターンと解き方を手で覚えるべし」がモットー、理論理屈をキチンと解説する「理解型」、簿記系YouTubeでは断トツ1位、簿記テキストは約10年間amazon1位とぶっちぎりの結果を出し続けている。大学で経営工学分野を専攻し、管理会計を中心にビジネス系の科目を学び、簿記検定やIT系の資格を取得、経営コンサルタントとして独立し、フリーランスとして活動、2025年3月時点で登録者数は51万人。
いろんな教材に手を出したくなりますが、
情報源は1つに絞ります。

同じ講師を繰返し視聴することで、
わからない箇所が探しやすくなり、
辻褄が合うので理解が深まります
理論理屈を理解することで応用が効き、
合格率も上がり
何より簿記の考え方が長期的に身につきます。
全動画を3周すると、
嫌でも理解が深まっていきます。1周目:理解できなくてよいので見る
2周目:全体像が掴めているので
詳細が少し理解できてくる
3週目:詳細でわからなかった部分が
理解できてくる
3周で8割理解できるので合格率50%程度、
更に1,2周することで
合格率が80%〜90%まで上がります。

聞くだけもよいですが、
動画自体を見ながらの方が
理解は深まります
ふくしままさゆきさんの電子書籍「ホントにゼロからの簿記3級」
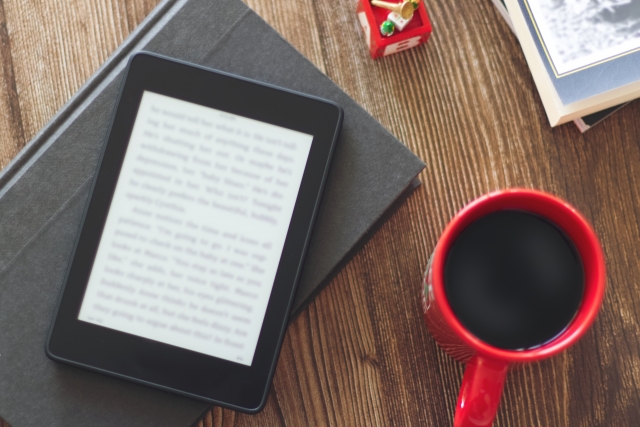
内容はYouTubeとほぼ同じですが、
動画が見られないの時や
文字で読みたい時などは
書籍でインプットすると
より理解が深まります。
Amazon Prime会員なら無料で読めます(Prime会員でなくても99円で購入可)。
同じ講師のテキストを使用すると、
一貫性があるので効率よく学習できます。

向き不向きもあるので、
書籍は必須ではありません
過去問、予想問題を解く

過去問・予想問題を最低5回解く
理由は以下の6つ。
1. 出題パターンに慣れるため
試験では仕訳・帳簿・決算といった
基本的な問題が繰り返し出題される

複数回解くことで、
問題の出題傾向を把握し、
本番で落ち着いて対応できます。
2. 時間配分を身につけるため
試験時間は60分、
実際に解いてみると時間が足りないことが実感できる

過去問を解くことで、
どの問題にどの程度の時間をかけるべきか、
自分なりの時間配分を確立できます
3. 実戦的なミスを減らすため
理論的に理解していても、
計算ミスや記入ミスで得点を落とす

過去問を繰り返し解くことで、
よくあるミスを自覚し、
本番でのミスを減らせます
4. 本番の形式に慣れるため
試験は3問
「仕訳問題」「帳簿作成」「試算表や精算表の作成など」で構成

どのような形式で問題が出るのか、
どの部分が得点源になるのかを知ることで、
効率よく点を取る戦略を立てられます
5. 苦手分野を特定し克服するため
自分の苦手分野が明確になる

例えば、仕訳問題は得意でも試算表作成が苦手な場合、
重点的にその分野の対策をすることで合格に近づきます
6. 出題傾向の変化に対応するため
毎回同じ問題が出るわけではない

最新の過去問・予想問題を解くと、
最近の試験の傾向を把握し、
出題形式の変化に対応する力をつけることができます
過去問、予想問題の無料Webサイト
無料で利用できるサイトを紹介します。
| ネットスクール | 3回分の模擬試験が可能。CBT方式を受ける方は本番に近いカタチで受けられる。 点数は表示されるが自分の回答と正解が出ないため、どこが間違っていたのか確認できないのが欠点。 |
| TAC | 問題数は少ないが無料登録すれば追加の模擬問題も入手可。 |
| CPAラーニング | 3回分の模擬が可能。解説動画もあり理解度アップに役立つ。 |
| 商工会議所 | 解説はないが本家なので精度は高い。 |
| Study Pro | 予想問題2回分とプラス苦手分野の問題。 |
| 簿記検定ナビ | 2回分の模試アリ。 |
| 資格の大原 | 解説はないが最後の仕上げには向いている。 |
これらを1周実施するだけでも相当チカラがつきます。

無料でこれだけあるので、
有料の教材は不要です
勉強の進め方
先にまず申し込んでしまう

最初に行うことの中で一番大事。
人間はだらけてしまう生き物なので、目標がないとなかなか実行しません。
逆に期日が決まるとサクサク進められます。
私の場合は統一試験を選択
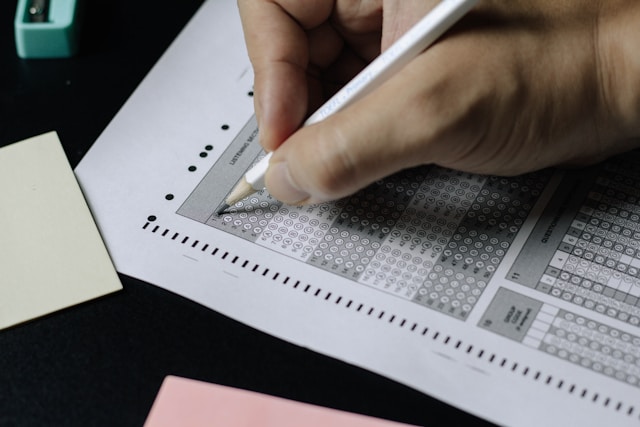
少数派かもしれませんが、
私はずっと紙で練習していたので、
紙で書き込める統一試験を選択しました。
同じ日に受験する人が多いので自分も頑張ろうという気になるし、
年3回しかないので目標がわかりやすく追い込みやすい、
というメリットがあります。
結果的にネット試験は受けなかったので、どちらがよいとは言い切れませんが、
個人的には統一試験オススメです。

紙なのでメモも書きやすいです
過去問・模擬試験の実施方法

模擬試験は事前に時間配分を決めておいて、
実際に掛かった時間を計測します。
私の場合、時間配分は以下で設定。
- 「問1=15分」
- 「問2=10分」
- 「問3=30分」
- 「見直し=5分」
→計60分

だいたい時間が足らなくなるので、
時間を掛けすぎていないか
計測しながら実施します
このやり方により
「問2に時間を掛けすぎている」と気付き、
”時間が掛かりそうなところは飛ばす”
という作戦を立てることができました。
そして、採点後に反省点を記録
反省点を目に見えるカタチにすることで、
自分で認識し
次の模擬の時に意識して取り組めて、
点数も上がります。

忘れないうちに改善点を言語化することで、
次回の点数が格段にアップします
試験当日の心構え

試験当日に大事なこと7ヶ条を
お伝えします。
私はこれを当日持参し、
試験直前に何度も読み返しました。

当日は緊張しがちです。
冷静さを保つためにも
とても力になりました。
時間が掛かる問題は潔く飛ばす
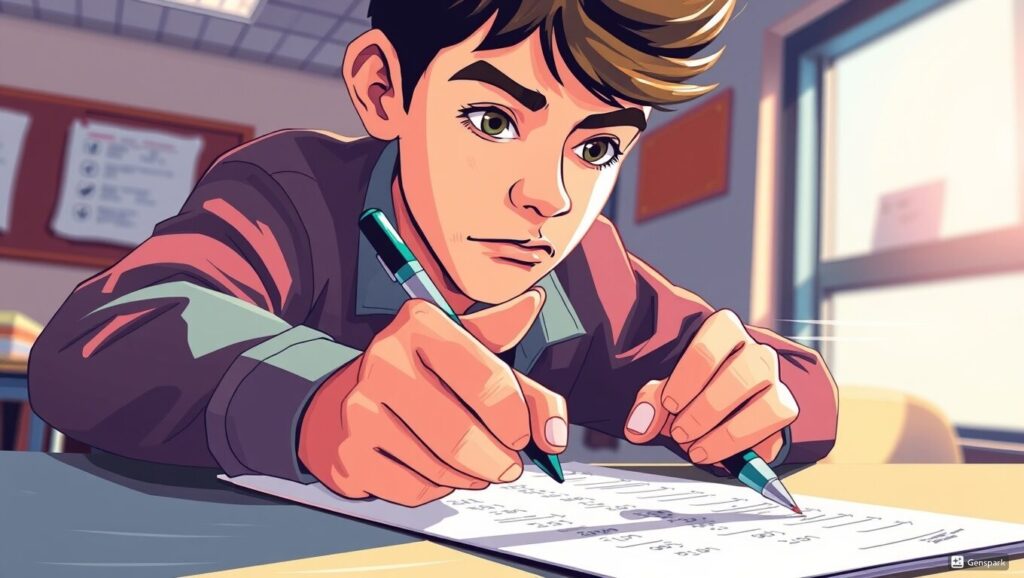
試験は70点取れれば合格、
逆に30点は落としても問題なし。
最初の方に出題された
問題文が長い設問や難易度の高い問題に
時間を掛けすぎて、
後の方にあった
簡単な問題に着手できずに点数を落とす、
というのがよくあるもったいないパターン。

簡単な問題は必ずあるので
それを優先して、
残りは時間が余ったら取り掛かる、
くらいがベストです。
問題文をきちんと読む

急いでいると
問題文の重要なところを見落としがち。
「建物の一部は別時期に取得」や
「貸引あり/なし」など。

思い込みがあると
単純なところで点数を落とします
焦っていると思った時こそ、
落ち着いてきちんと問題文を読みましょう!
借と貸を逆にしない
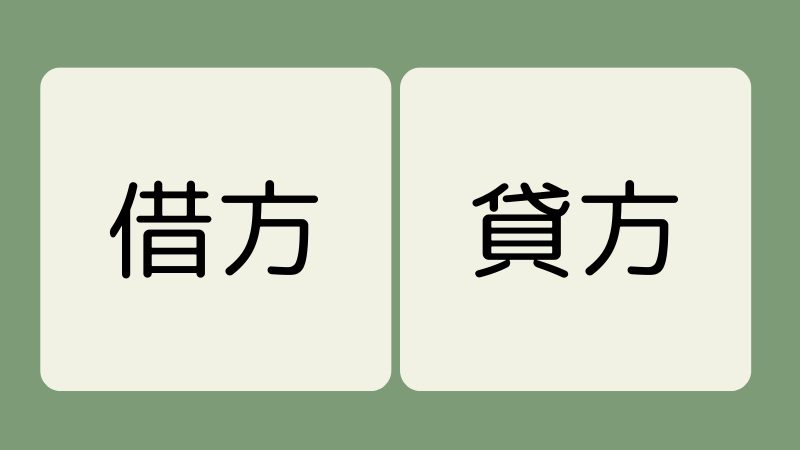
頭ではわかっていても書く時に、
なぜか借方と貸方を逆に書いてしまうことがありました。

私だけかもしれませんが、
念の為入れておきました
仕入には取得原価を含める

個人差はあるかもしれませんが、
結構忘れがちなポイント。

取得原価には
送料や手数料などがあります
問題文に「送料xxx円が発生した」
などの記載があるので
見落とさないように!
記入ミスや記入漏れがないように

試験本番では
いつもできていることができなくなります。
単純な計算ミスもやりがち。

解ける問題を
凡ミスで落としてしまうのは、
すごくもったいないです
凡ミスを防ぐには「見直し」が大事。
一通り終わっても気を抜かずに、
時間がある限り最後まで粘ることで合格点に届く。
他人との競争じゃない
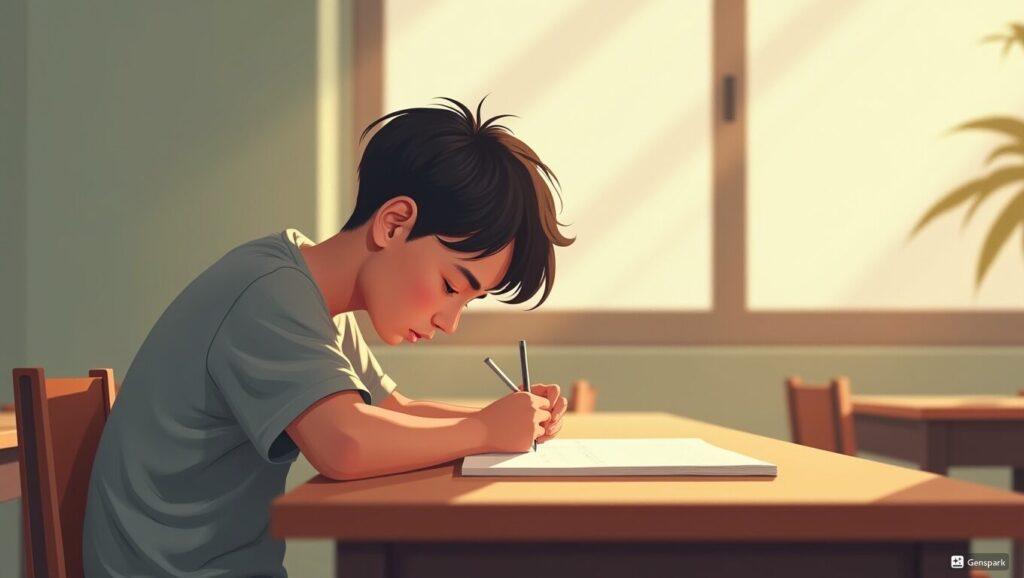
大事なことなので何度も言いますが、
「もし全員7割取れたら、全員合格」です。

隣の人が落ちようが合格しようが、
自分の点数には何の影響もありません
電卓を早く叩く音や紙に書き込む音が聞こえて焦りがちですが、
それはそれとして聞き流せるようになると無敵です(笑)。
何度でもすぐに受けられる
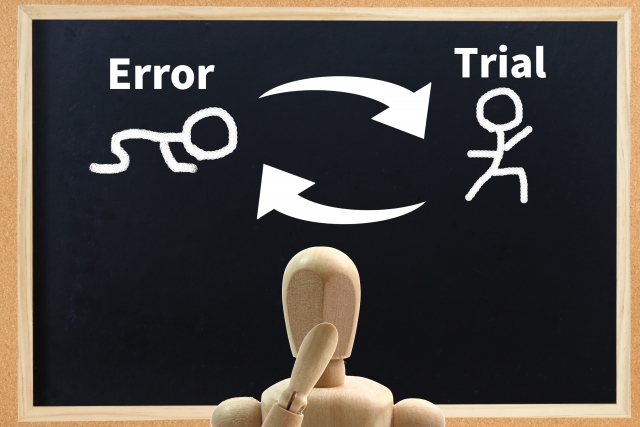
人間なので誰しも緊張したり、実力が出せない時もあります。
そんな時は「またすぐに受けられる」と思うと気が楽になります。
一回落ちたら
一生受けられないわけではありません。
合格するまで何回でも受けられます。

そう思うと
落ち着いて実力が出せて、
結果合格することも多いです
統一試験は少し間は空きますが、
ネット試験はすぐに再受験可能です。
何かしら書く!最後まで諦めない
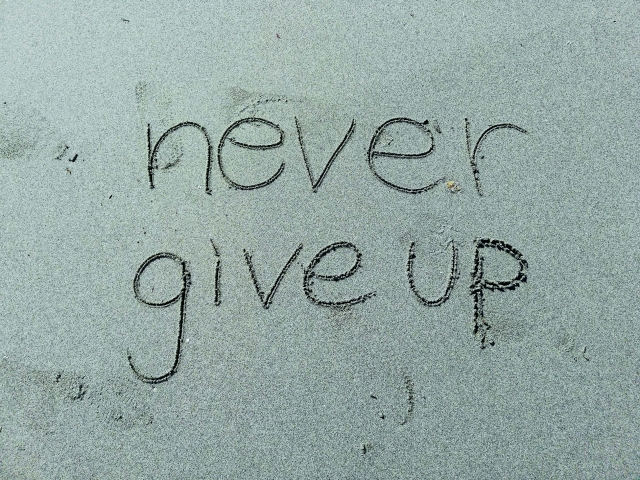
何も書かなければ絶対0点ですが、
何か書きさえすれば1%でも可能性が発生します。

「あきらめたら試合終了」です
せっかく時間を割いて受験しているのだから、
最後の1秒までもがきましょう!
まとめ
挑戦し続ければ、いつかは必ず合格できます。
では幸運を祈ります!
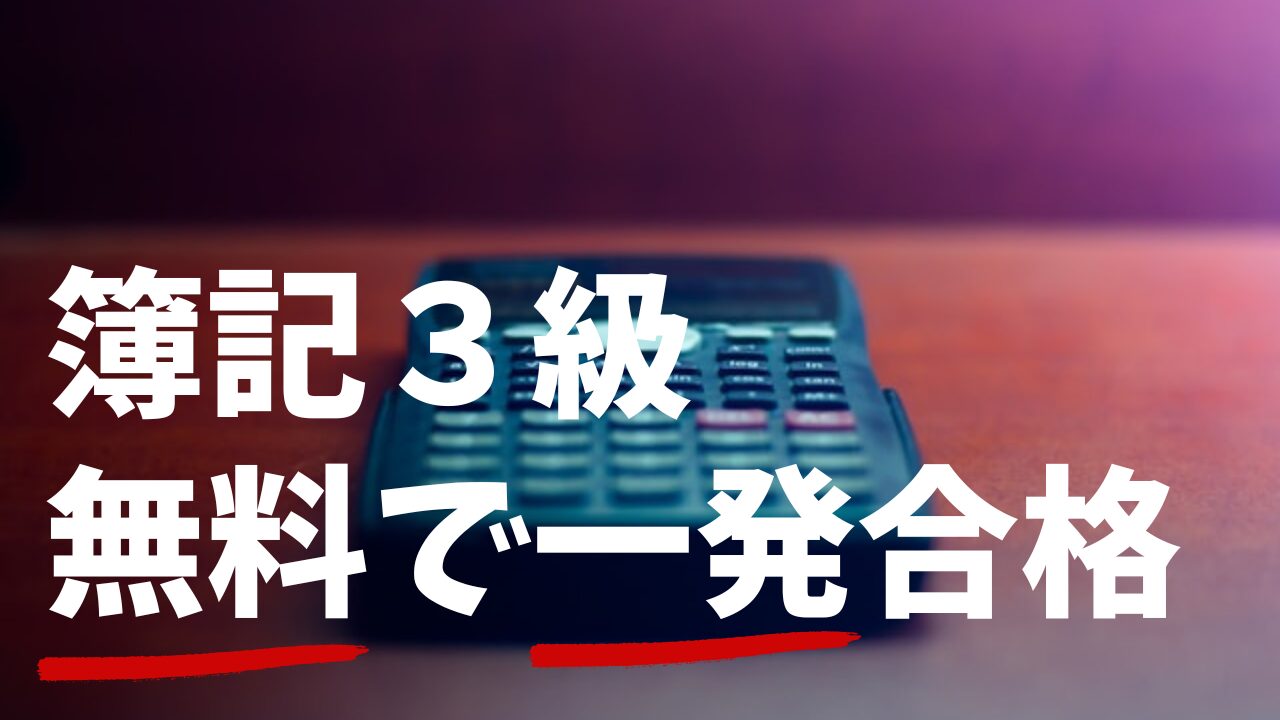


コメント